
【エッセイ】アーティスト猫沢エミが綴る『天国のイオからのメッセージ』
毎日の小さな喜びや幸せはもちろん、時には生きる上で大切なことを教えてくれるペットたち。 共に過ごす時間は、どんな瞬間も、かけがえのないものになるでしょう。 これまで4匹の保護猫と暮らしてきたミュージシャンで文筆家の猫沢エミさんは、2021年3月に愛猫イオちゃんを看取りました。大切な存在を失って見えてきたもの。猫たちから受け取った愛のカタチを綴っていただきます。
猫沢家の猫たち

成熟した“猫格”を持つ猫と人生を共にするということ
今日は皆さんに、今年の3月に扁平上皮がんで見送ったメスの老猫・イオの話をしようと思う。イオは、2019年の夏、仕事で出向いていた新宿の路上で餓死寸前のところを保護した我が家の4代目の愛猫だった。
イオのことを語るには、まず我が家の先代猫たちの紹介が欠かせない。2002年にパリへ一緒に移住し、その後、日本へ帰国して13歳11ヶ月で天寿をまっとうしたメスの初代愛猫ピキ、そして現在一緒に暮らしている10歳のオスの黒猫ピガと、9歳の茶トラ猫ユピの3匹は、いずれも生後3週間くらいで出逢った保護猫たちだ。ピキは、当時暮らしていたマンションのゴミ捨て場で直接保護した猫で、ピガとユピは、それぞれSNSの猫の里親募集情報で貰い受けた。
当時の私は、“共に人生を歩むなら、仔猫からがいい”という考えしか持っていなかった。もちろん仔猫や若い猫も、若年から病気になる可能性はある。それでもやっぱり、愛する猫たちとは少しでも長い時間を共にしたいという、ごく当たり前の発想だったと思う。そうした考えが、イオの出現でガラリと変わった。イオと暮らしたのは1年半という短い時間だったけれど、私は彼女にたくさんのことを教わった。
そもそも、猫も人間も様々なことを経験して大人になっていくところは同じ。仔猫期の反則に近い特別な可愛らしさは別として、長く猫と暮らして気づいたのは、精神が充実してはっきりした個々の猫格(人格、の猫版)を形成するのは、7〜8歳ごろだということ。飼い主の私と対等に、日々の生活を自ら組み立て、家のなかで彼らなりの役割を見つけるこの年齢の猫たちとの暮らしは、すこぶる心地がいい。私にとっての猫とは、ひとつの独立した存在であり、人間の所有物ではないから。イオが実際にはいくつだったのかわからないが、彼女にはおとなの猫だけが持つ、高い経験値がはじめからあった。
ひょんなことから知ったイオの過去。それは、元飼い主に捨てられ、約1年に渡る辛い路上生活を強いられたというものだった。荒波を越えて我が家にたどり着き、幸せをつかんだイオには肝の据わった揺るぎない意思の強さがあり、それはマンション暮らしのお坊ちゃまとして育った男子猫2匹にはない魅力だった。
路上生活を経験した猫とはとても思えない、社交的で礼儀正しいイオの立ち居振る舞いに驚かされたことは一度や二度ではない。たとえば、先住猫のピガとユピのテリトリーに入る時には、かならず「失礼しまぁ〜す!」と高らかに鳴いて知らせるなど、高年齢だからこその猫格の高みへと到達していた。だからこそ、ピガとユピの受け入れはごく自然で温かかったのだと思う。
ひとりと3匹で過ごした時間
話は前後するが、私にとっての多頭飼いの最初の猫は、ピガとユピだった。まず、ピガを保護主さんから貰い受け、彼が生後10ヶ月になった頃、ユピを別の保護主さんより貰い受けた。ピガにきょうだいを作ってあげようと思ったきっかけは、ほぼ成猫の体躯まで成長した頃、覇気が急になくなり、毎日つまらなそうにぼんやりしてしまったのが理由だった。そこでSNSで見かけてピンときた、茶トラの仔猫を貰い受けた。それがユピである。偶然ふたりとも、それぞれの保護主さん宅で先住猫との猫社会を経験していた。しかも、ユピの面倒を見てくれていたのが奇遇にもピガと同じオスの黒猫だったので、これは期待大!と連れ帰ると、ふたりはその日からすぐに仲良く遊び始めた。人間には到底真似のできないタテヨコ3Dで動く追いかけっこや、体当たりのプロレスができるようになったピガは、あっという間に精気を取り戻した。
かたやユピは、遊びのなかで猫同士のマナー(強く噛みすぎないことや、相手の気を読んで遊びを仕掛けるなど)をピガから自然に学んでいった。
はじめに私とピガの、一対一での信頼関係が生まれ、その後、ピガとユピの独立した小さな猫社会が生まれた。そこへやってきたのがイオだった。
そこには“吾輩は猫である”という自覚に基づいた猫社会と、“自分は飼い主(人間)とは違う生き物(猫)である”という自覚が生まれる。ややもすると飼い主は感情移入しすぎて、猫と人間は違う生き物だという線引きを失ってしまいがちだからこそ、この意識は飼い主にとっても大切なのだ。
イオと、ピガとユピが、まるできょうだいの契りを交わしたかのように強力な信頼関係を短期間のうちに築いたのを見て、私は彼らに“猫沢組”という名前をつけた。
猫沢組と過ごした日々は、新鮮な心地よさがあった。しかし、新しい暮らしがスタートして、1年5ヶ月たったある日、イオにがんが見つかってしまった。
余命2ヶ月の宣告から旅立つその日まで、ピガとユピは驚くほど細やかな見守りと優しさをイオへ注いでくれた。ふたりのうちどちらかが、片時も離れずイオの側について見守り続けてくれたのだ。その見事な連携は、人間の私が見ていても驚くほど鮮やかだった。
イオが私たちと共に暮らしたのは1年半だったにも関わらず、素晴らしい関係が築けたのは、人間の私が介入することのない独立した猫社会があったからだと思っている。そして、イオを幸せにしてやれたのは、決して私という人間ひとりの力だけでなく、3匹が作る猫社会の信頼関係と絆があったからなのだ。
イオが教えてくれた愛と心のつながり
動物と人間は違う生き物である、という基本観念がもっとも大切になってくる場面が、見送りの時だ。人間よりも短命な彼らは、誕生から死までの一生を、私たちが生きている時間に丸ごとすっぽり収まる形で見せてくれる。そのことは、“出逢いの瞬間に約束された哀しみ”であるのと同時に“生き物はいつかかならずみな死ぬ”という自然の掟を教えてくれている。
死と共に訪れる哀しみは、彼らがくれる純粋な愛と同じく純度が高いから、時に人間の大切な存在を失うよりも辛いのだ。取り残されて哀しむ人間の私たちにも、かならずやってくる未来の心構えを教えてくれる動物たち。そして、哀しみをくぐり抜けた後に見えてくる、生のきらめきと幸せな時間を見つめることの方が、死という一過性の点にとらわれることよりもずっと大切だと、彼らは身を以て教えてくれる。
それはそのまま、自分を愛してくれた飼い主に、最期の時まで限りある命を精一杯幸せに生きて欲しいという命のメッセージであり、私たちがいつかあの世に旅立つ時、死の恐怖に怯えることのない、大きな安らぎへと変わるのだ。
初代愛猫のピキを亡くした2010年、私は40歳で、まだ両親の看取りや近しい友人の死を日常のものとして感じるには若かった。そんななか、初めて経験した愛猫の死の衝撃は大きく、逝去から数日間の記憶が曖昧なほど、私は打ちのめされた。それから11年が経ち、両親の看取りも、何人かの友人の死も経験して、ある程度の死生観を獲得した状態でイオの見送りに向かった。
ところが、そんな経験などひとつも役に立っていないかのように、イオの死はまったく固有の新しい哀しみでしかなかった。その理由は、私と出逢う前のイオの不憫な猫生を思う深すぎる慈しみと、一緒に暮らした1年半という時間の短さに起因していたからかもしれない。そして私はイオを愛するあまり“人間と動物は違う生き物である”という基本的なライン引きを忘れてしまっていたようにも思う。
“1年半”を短いと思うことも、人間の勝手な時間の尺度だと気づいた。彼女にとっての1年半は、それまで苦労続きだった長い猫生を忘れてしまうほど、幸せに満ちていたと思う。イオは、その1年半の記憶を抱いて、天国へ旅立った。つまり、その1年半は永遠という時間へ姿を変えたのだ。
愛する存在を失う哀しみを受け止めて気づいた、イオからのメッセージ
イオの見送りには悔いがなかった。余命は2ヶ月との宣告を受けてから、たったの48日間で彼女は逝ってしまったけれど、旅立ちの日が近いとわかっていたからこそ、私は仕事のスケジューリングをできるだけコントロールして、イオの最後の日々を丁寧に、味わうかのように共に過ごした。
イオの場合、自然死を望めば過酷な最期が待っていることも事前にわかっていたので、その兆候が出ると迷うことなく安楽死を選択した。もちろん簡単に決められるようなことではなかったし、これまでの人生で最も悩みぬいた決断でもあった。彼女とのかけがえのない日々を過ごしながら、「私がイオなら、どう最期の時を迎えたいか?」と繰り返し自問自答した末に見つけた答えは、イオ逝去後の納得や立ち直りに、大きな支えとなっていく。私がイオにあげられる最大の贈り物、それが安らかな最期だった。
それでも見送った後、この世に取り残された私は、強烈な喪失感と新しい哀しみに再度向き合うことになる。この原稿を書いている今日はイオの半年目の命日で、ようやく私は彼女の幸せだった猫生に対して、新しいイメージを持てるようになった。そして、イオからのメッセージに気がつくことになる。
「ワタシはあなたを苦しませるために、あなたと出逢ったわけじゃない。幸せをあげたくて、その幸せであなた自身が幸せになることを望んで出逢ったの」
イオを亡くしてからの数ヶ月は、ろうそくとお花を切らさずに祭壇へ捧げ続けた。どちらも短命で光を放つものであるそのふたつを切らすことは、イオとの交信が途絶えるような気がしてとても怖かったのだ。ところが、毎朝祭壇を整えてイオに話しかけ、丁寧に弔っていくうちに、向き合っているのは自分自身であり、幸せに猫生をまっとうできたイオへの祝福なのだと少しずつ思えるようになった。
弔いなど残された人の自己満足だと切って捨てていた若かりし頃の私は、まだ“失えない大切な存在を誰もが必ず失う”という、生きる宿命のなんたるかを知らなかった。丁寧な弔いは、亡くなった大切な存在と、その存在がこの世に残した愛する人の双方に、幸せを気づかせる大切なイニシエーション。そして、無理に笑ったり、心に言葉を押し込めたり、また逆に誰かに話したりもしなくていい。泣きたい時に泣き、想い、自然に流れる時のままに身を任せるのがいい。
するとある日、天国からのメッセージが届く。泣けるほど愛した存在が自分の人生にあることの素晴らしさと、生をまっとうした大切な命が、残された人の心の中でふたたび蘇る。この命に死はない。前を向いて生きていく人と共に、第二の生を謳歌していく。私は今、そんなふうに考えている。

・当記事に掲載の情報は、執筆者の見解で、ライオン株式会社の見解を示すものではありません。
編集 ノオト
- トップページ
- 【エッセイ】アーティスト猫沢エミが綴る『天国のイオからのメッセージ』


















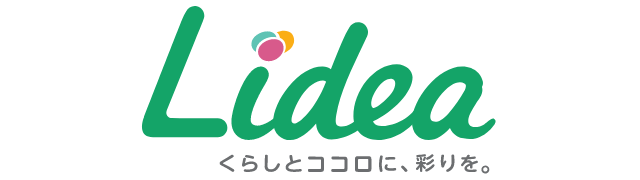





下記のコメントを削除します。
よろしいですか?
コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容コメント内容